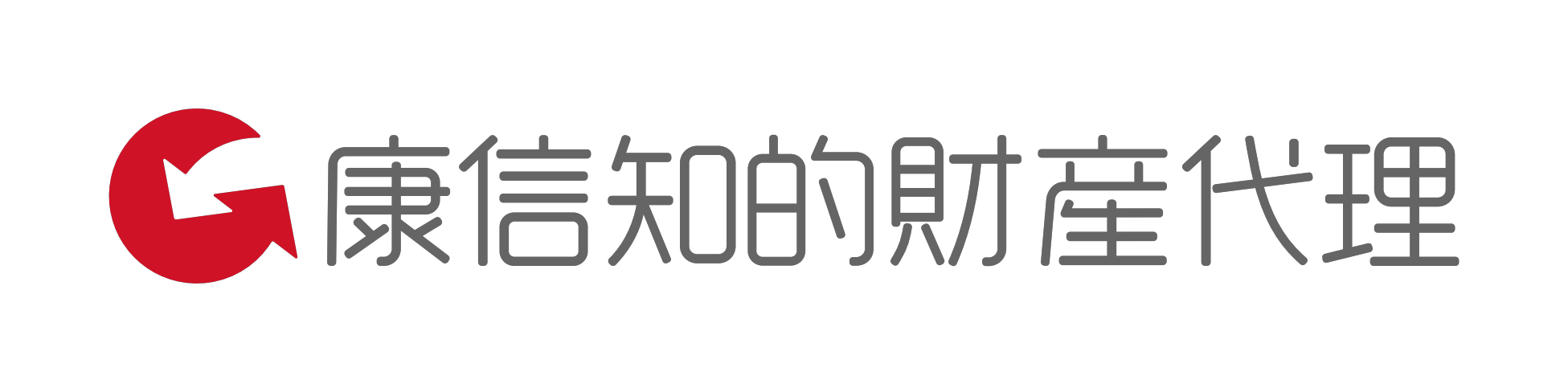ご存知のとおり、「専利権評価報告書」は、国家知識産権局が要請に応じて、関連する実用新案や意匠に対して調査、分析、及び評価を行った後、作成する公式報告書であり、専利権侵害紛争の審理と処理の証拠として使用できます。専利権者、利害関係者、または被疑侵害者とされる者は、自発的に「専利権評価報告書」を提出することもできます。
専利権侵害訴訟においては、当事者が「専利権評価報告書」を提出するか否かが、裁判所における侵害訴訟の審理の進行に影響すると思われます。なお、「専利権評価報告書」の提出は、侵害訴訟の審理の結果に直接影響しますか?答えは「はい」です。
事例
当所代理したB社が意匠権侵害で訴えられた意匠権侵害訴訟において、原告であるA社が本件意匠権の「専利権評価報告書」を提出しなかったため、裁判所は原告の訴えを棄却するという「民事判決書」を下しました。その後、二審裁判所も一審の棄却決定を維持するという判決を下しました。
「専利法」第66条第項には、「専利権侵害紛争が実用新案権又は意匠権に係る場合、人民法院又は専利業務管理部門は専利権者又は利害関係者に対し、専利権侵害紛争を審理し、処理するための証拠として、国務院専利行政部門が関連の実用新案又は意匠について検索、分析、評価を行ったうえ作成した専利権評価報告書を提出するよう要求することができる。専利権者、利害関係者又は被疑侵害者は自発的に専利権評価報告書を提示することもできる。」と明確に規定されています。
本件において、原告であるA社が意匠権侵害でB社を訴えました。したがって、特許法の規定により、侵害訴訟を受理した裁判所は原告に対し、国家知識産権局が発行する意匠権評価報告書の提出を要求することができます。実際には、A社が裁判所に訴状を提出したところ、裁判所は専利権評価報告書が必要と既に明確に説明したが、A社は「特許評価報告書を提出しないことを決定し、本件訴訟の関連するリスクを知っている」ことを示す「状況陳述書」を裁判所に提出しました。
「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」の第4条第1項には、「出願日が2009年10月1日以降の実用新案権又は意匠権について侵害訴訟を提起する場合、原告は国務院専利行政部門より発行する専利権評価報告書を提出することができる。また、人民法院は原告に対し、検索報告書又は専利権評価報告書を提出するよう要求することができる。原告が正当な理由なく提出しない場合、人民法院は訴訟の中止を決定したり、原告に不利な結果を負わせるよう命じたりすることができる。」と規定されています。
上記から見ると、専利権侵害訴訟においては、「特許権評価報告書」の提出を怠ると不利な結果を負う必要があることが分かります。
当所弁護士は、被告であるB社の訴訟代理人として、依頼を受けてから、本件意匠権の安定性を調査・分析し、本件意匠権が不安定であることを証明する証拠として、本件意匠特許の出願日よりも前の公開日を有する既存の意匠文献を裁判所に提出しました。
その直後、裁判所は原告であるA社の提訴を棄却するという民事判決を下し、下記のように意見を述べました。原告のA社は、当院が釈明と督促を行ったにもかかわらず、正当な理由なく合理的な期間内に専利権評価書の提出を拒否しているため、裁判所としては、本件意匠権が不安定であると考える理由があり、法によりその提訴を棄却します。A社は、自社意匠権が安定したことを証明できれば、別途訴訟を起こすことができます。
そして、原告のA社は、一審の判決を不服として、二審裁判所に控訴し、「専利権評価報告書は行政決定ではなく、特許権が安定したかどうかの初歩的な参考資料に過ぎない。一審裁判所は、直接提訴を棄却すべきではなく、訴訟を中止するか、起こり得る不利な結果を負うよう命令する決定をすべきである。」と主張し、また「最高人民法院が審理した(2020)最高法民再383号案件裁定書」(主な判決内容:原告が裁判所の要求に応じて専利権評価報告書を提出しなかったが、訴訟に関わる専利権が依然として適法かつ有効であることを証明できる場合、専利権評価報告書の提出を拒否したことを理由として、原告の提訴を棄却すべきではない。)をもって、「同案同判」を二審裁判所に請求しました。
二審裁判所は、審理後、次のように判決を下しました。「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」の第4条第1項の規定により、人民法院は必要に応じて、原告に対し、検索報告書又は専利権評価報告書を提出するよう要求することができます。原告が正当な理由なく提出しない場合、人民法院は訴訟の中止を決定したり、原告に不利な結果を負わせるよう命じたりすることができます。本件において、B社が一審において第三者の先行意匠権を提出したことにより、本件専利権の安定性に疑問があるようになったため、当裁判所は、本件審理の必要性を踏まえ、A社が専利権評価報告書、又は自社専利権利が適法かつ安定したことを証明するその他の証拠を提出する必要があると判断しました。しかしながら、一審裁判所が何回も説明したことにもかかわらず、A社は、正当な理由なく特許評価報告書を提出しなかったため、不利な結果を負うべきである。したがって、一審裁判所のA社の提訴を棄却するという判決は不適切ではありません。なお、(2020)最高法民再383号案について、国家知識産権局が審査後、その関連専利権の有効性を維持すると決定したため、本件とは基本的な事実が異なります。よって、A社の控訴請求が成り立てず、原告の控訴を棄却し、原審判決を維持します。
上記事例から見ると、「専利権評価報告書」は実用新案権・意匠権侵害訴訟の審理手続きに影響を与えるだけでなく、評価報告書の有無は、裁判所による審理の中止の有無にも影響し、さらに、本件事例のように、裁判所が原告の提訴を直接棄却するなど、侵害訴訟の結果に直接影響を与える可能性もあります。裁判所の上記判決は、専利権侵害紛争の審理および処理における証拠としての「専利権評価報告書」の役割を反映しています。そのように判決しないと、専利法における実用新案権および意匠権の評価報告制度が無意味になります。