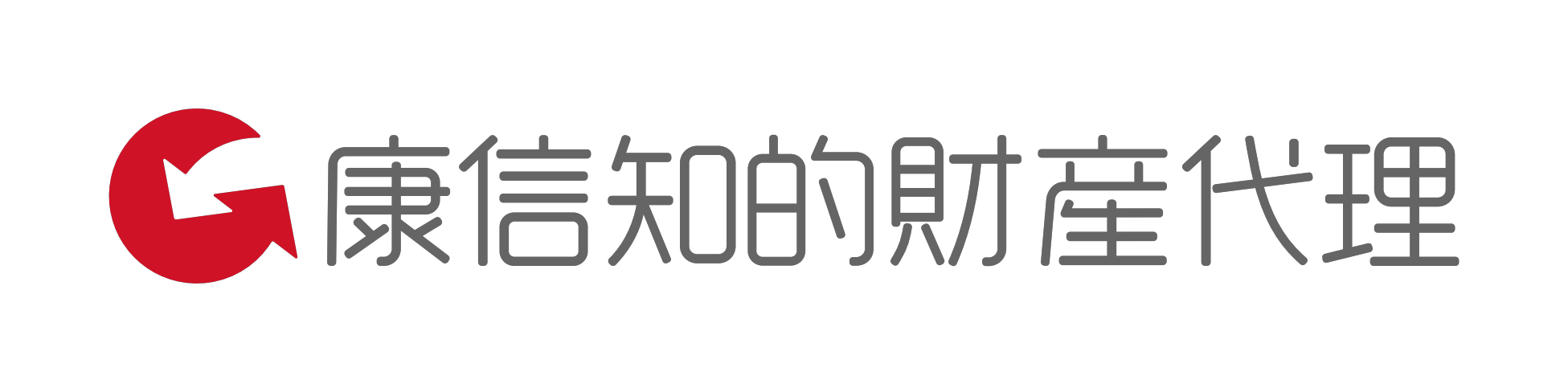商号と商標はどちらもビジネスで企業の識別マークで企業の評判の重要な媒体となっており、どちらもテキスト形式で表示できる。多くの市場主体の会社名(商号)と商標は同じである。そのため、実務上、商号権と商標権の抵触に関する紛争が多くなっている。本稿では、企業商号に係る行政摘発の種類をより正確に把握するために、商号権と商標権の実務上の抵触とその解決策について論じる。
商号とは、企業が法律に基づいて取得した名称であり、企業が事業活動を行う際に他の経済主体と区別するための象徴的な名称であり、企業が事業活動を行う際に使用する唯一の特定な名称である。商号は本質的には商業的なロゴであり、識別の点では商標と同じ機能を有する。商号と商標はどちらもビジネスでは識別マークで企業の評判の重要な媒体となっており、どちらもテキスト形式で表示できる。数多くの市場主体の会社名(商号)はその商標と同じである。
一、企業の商号権と商標権の相違点
1.権利の特徴が異なる
商号権は、一般民事権における人身権(人格権と身分権)の範囲に属し、自然人の氏名権に相当する。商号権は人身権のの範囲に属して必ず特定の企業に付随するものであるため、次のような特徴がある。
まず、商号権は、企業設立時に法律に基づいて取得しなければならない基本的な民事上の権利である。言い換えれば、企業が法律に基づいて商号権を取得することは適法かつ必要なことである。
次に、法律により、企業は1つの名称しか登録して使用することができない。つまり、法律により、1社の企業は1つの名称に対してのみ専用権を享受することができる。
また、企業商号権が個人的な性質を持つため、商号権の有効期間は「企業の設立とともに始まり、企業の終了とともに終了する」。つまり、特定の企業と「運命を共にする」ことになる。
さらに、企業は自社が使用している商号の使用を同時に他者に許諾してはならない。つまり、同じ地域内で、2 つ以上の企業が同時に同じ商号を使用してはならない。
商標権も民事上の権利であるが、人身権ではなく知的財産権である。したがって、商標権は商号権とは異なる性質を持っている。
まず、企業が法律に基づいて設立された後、通常の状況では、企業は自身の経営状況と市場競争のニーズに基づいて、法律に基づいて商標を登録するかどうかを決定する権利を有する。つまり。企業が商標を登録し、商標権を享受するかどうかは任意である(国による強制登録の場合は除く)。
次に、企業は法律に従って複数の商標を出願することができ、それによって複数の登録商標に対する専用権を所有することができる。
また、企業は商標権者として、法律に従って登録商標を他人に使用許諾することができ、また登録商標を他人に譲渡することもできる。
さらに、企業商標権には明確な有効期間があり、即ち、10年となっている。 10年の有効期限が切れた後は、法律に従って更新することができる。1回の更新により有効期間が10年延長され、更新回数に制限はない。
2.商号権と商標権の取得方法と権利の範囲が異なる
商号権と商標権の取得は何れも法律に従って登録しなければならない。商標権を取得するには、法律に従って国家知識産権局に登録を出願するしなければならない。商号権は、法律に基づき県級以上の各級市場監督管理部門(県級を含む)に登録申請することにより取得することができる。つまり、商標登録は国家知識産権局によって統一的に登録され、商号の登録は会社の性質と規模に応じて国家または地方の市場監督管理部門によって階層的に登録される。
商号権と商標権は取得方法が異なるため、対応する権利範囲が異なっている。つまり、商号権主体が法律に基づいて享有する商号権利は、名称登録機関の管轄する行政区域内でのみ有効であり、保護されます。この点について、「企業商号登録管理規則」第3条には、「企業が登録を申請する際には、登録機関の認可を受けなければならない。企業商号は認可登録された後にのみ使用することができ、規定の範囲内で専用権を有する」と明確に規定されている。
そのため、企業の商号登録機関によって、その商号権の権利範囲が異なる。例えば、国家市場監督管理総局が法律に基づいて登録した企業商号は、同じ業界内では全国で専用権を有するが、県の市場監督管理部門が登録した企業商号は、その県内でのみ専用権を有する。商標登録は全国統一登録方式で行われるため、国家級企業であろうと地方企業であろうと、法律に基づいて取得した商標権の有効範囲は全国一律となる。
二、企業商号権と商標権の抵触の状況
一般的に、商標権と商号権が抵触するかどうかを判断する場合、両者の間に混同があるか、あるいは混同する可能性があるかが基準となる。
最高人民法院の「現在の経済情勢における知的財産権裁判の全体的情勢に関する若干の問題に係る意見」第10条によると、企業商号が目立つように使用され、先行登録商標の専用権を侵害した場合、法律に基づいて商標権侵害として処理される。企業商号が目立つように使用されていなくても、その使用が市場の混乱を引き起こし、公正競争に違反した場合、法律に基づいて不正競争として処理される。実務において、商号権と商標権の抵触は、次の2 つの状況がある。
1.企業名称における商号を目立つように使用し、登録商標専用権の侵害になる状況
「最高人民法院による商標をめぐる民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」第1条第(1)項には、他人の登録商標と同一または類似の文字を会社の名称として使用し、同一または類似の製品に目立つように使用して、関係公衆に誤解を招くおそれがある場合、他人の登録商標専用権を毀損する行為に該当すると規定されている。
権利者が適法に登録された商号を目立つように使用したり、不法に使用したりすることが商標権侵害に該当する理由は、この場合の商号の使用が商標法上の使用の定義を満たしており、商標法上の標識や区別の機能を有しているためである。即ち、このような場合、商号は商号としてではなく、商標として使用されることになる。こういうような侵害事件の主な特徴は、商品、商品の包装や容器、商品取引文書、または広告、展示会、及びその他の商業活動において、商号またはその略称や頭字語が目立つように使用されていることである。
2.企業名称における商号を目立つように使用していないが、不正競争になる状況
「商標法」第58条には、「他人の登録商標または未登録の馳名商標を企業名称として使用することが公衆を誤認させ、不正競争に該当する場合、中華人民共和国不正競争防止法に基づいて処理される。」と規定されている。商号を目立つように使用していないが、その使用が消費者に混乱や誤解を引き起こし、公正な競争に違反する場合は、不正競争に該当する。
『最高人民法院による「中華人民共和国不正競争防止法」の適用に関する若干の問題の解釈』第11条には、「事業者が、他人に一定の影響力を有する社名(略称、商号等を含む)、社会団体名(略称等を含む)、氏名(筆名、芸名、翻訳名等を含む)、ドメイン名の主要部分、ウェブサイト名、ウェブページ等に類似する標識を無断で使用し、他人の製品であると誤認させたり、他人と特定の関係があると誤認させたりした場合、当事者が不正競争防止法第6条第2項及び第3項に規定された状況に該当すると主張する場合、人民法院はこれを支持すべきである。」と規定している。また、第12条には、「人民法院は、ある商標が不正競争防止法第6条に規定する『一定の影響力を有する』商標と同一または類似であるか否かと判断する場合、商標の同一または類似を判断する原則と方法を参照することができる。」と規定されている。
商標の同一または類似を判断する原則と方法については、「最高人民法院による商標をめぐる民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈」第 10 条に、「人民法院は、商標法第 57 条第 (1) 項と第 (2) 項の規定に基づき、以下の原則に従って商標の同一または類似を判断する。(1) 関係公衆の一般的な注目度を基準とする。(2) 商標の全体比較と主要部分の比較の両方を行い、比較対象を分離して個別に比較すべきである。(3) 商標の類似を判断する際には、保護を求める登録商標の識別性および知名度を考慮すべきである。」と規定されている。